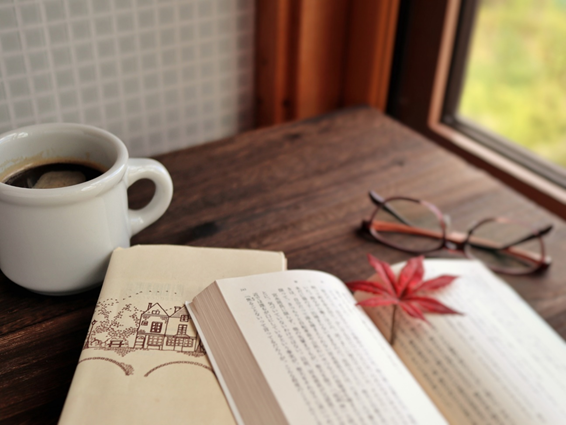
2020/09/25 【お墓と供養】
まだまだ暑い日もありますが、日が暮れるのが日に日に早くなり、吹く風や虫の声に秋の訪れを感じます。自粛生活も長くなり、それぞれに家での生活に工夫をされているようです。
インターネットやゲームなど最新の技術も楽しいですが、紙とインクの匂いもまた秋の訪れを感じさせます。
少し原点に戻って、アナログな「読書の秋」を楽しんではいかがでしょうか?
ここではタイトルに「お墓」がつく作品や、テーマに「葬儀」がある小説をいくつかご紹介したいと思います。
<朱鷺の墓 著者:五木寛之>
日露戦争下の城下町、金沢を舞台に5歳で花街へ売られてきた美しい芸妓とロシア貴族出身の青年将校の恋を描いた小説です。戦争という時代の波に翻弄されながらも、お互いを求めて、日本、ナホトカ、ウラジオストク、ペトログラードと舞台はめぐります。壮大なスケールで描かれた読み応えのある作品は、秋の夜長にぴったりです。
<野菊の墓 著者:伊藤左千夫>
誰でも一度はこの作品名に触れ、読んだことがあるのではないでしょうか?雑誌「ホトトギス」に発表されたこの作品は15歳の少年斎藤政夫と2歳年上の従姉、民子の物語です。
お互いの間に淡い恋心を感じながらも民子が年上のためにその思いは遂げられず、町の中学に進学した政夫が帰省して知るのはその愛しい人の死でした。
今の時代ならなんでもないようなことが、悲しい結末になってしまう時代。すでに古典とも呼べるこの作品を今一度振り返るのもよいですね。
<火垂るの墓 著者:野坂昭如>
第二次世界大戦下、両親を亡くした14歳の兄と4歳の妹が、引き取り先の叔母とうまくいかずに二人きりで生き抜こうとするが、妹が栄養失調で亡くなってしまう悲劇が描かれています。この作品を原作としたアニメーション映画が有名ですが、テレビドラマなども作られています。毎年、終戦日近くになると必ずといっていいほどアニメーション映画が放映されており、多くの方が一度は耳にしたタイトルだと思います。
<四十九日のレシピ 著者:伊吹有喜>
母が亡くなって気力を失った父親のもとに一人の少女が訪れます。少女は生前の母に頼まれたといって四十九日の間、家事などを受け持ちます。
大切な人を失った家族が、また明日を生きていくという再生の物語です。
前に挙げた3作が悲恋や悲劇をテーマとしているに対し、こちらの作品は、人を失った悲しみから周囲が立ち直っていく物語。現代が舞台でときにユーモラスに遺族の様子を描いています。
「死」が必ずしも終わりだけではない、未来へと遺されたものを導く役割も果たしていると気づく心が温かくなる作品です。
いかがでしょうか?モニターの光から少し遠ざかってページをめくっていくのも穏やかな気持ちになりますよ。